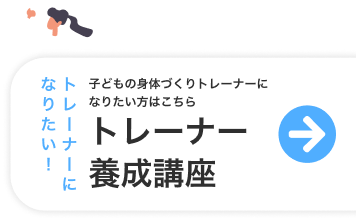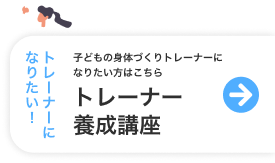子どもの健康をサポートする身体づくりトレーナーが、
全国に多数在籍しています。
ぜひお近くのトレーナーを検索してください
子どもの健康をサポートする身体づくりトレーナーが、全国に多数在籍しています。 ぜひお近くのトレーナーを検索してください
MAPで検索する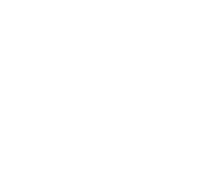
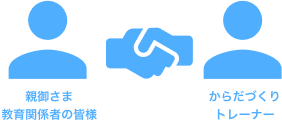
近くに住んでいる身体づくり
トレーナーとコンタクトがとれます
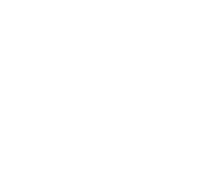

学校や各種習い事にトレーナーを呼んで
ワークシショップを開催したり
オンラインレッスンを受けたりできます
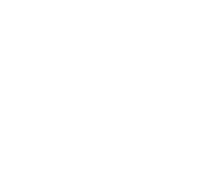
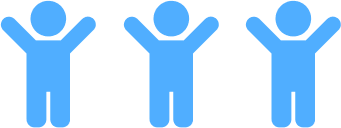
各種プロのトレーナーが
身体づくりの面から
子どもの健康をサポートします!

地元のトレーナーを
検索できます

身体づくりに関する
コラムで学べる

オンラインや現地開催の
ワークショップに参加
すでに全国では、資格を持つ子どもの身体づくりトレーナーによるワークショップが多数開催されています。公民館や学校の体育館など、ご指定の場所に、トレーナーがワークショップをお届けします。
まずはお気軽に、お近くのトレーナーにお問合せをしてみてください。お問合せは、各トレーナーの紹介ページにあるお問合せフォームや、トレーナーのSNSなどから行っていただけます。
特別な訓練を受け体軸理論を習得した、様々な資格を持ったトレーナーが全国に在籍しています。体づくりの基礎「体軸」のプロから「ダッシュ」に特化した「走り方」のコツを伝授できるプロなど…子どものお悩み・伸ばしたいことに合わせたスキルを持つトレーナーが多数!ぜひお近くのトレーナーをMAP上で探してくださいね。